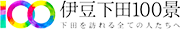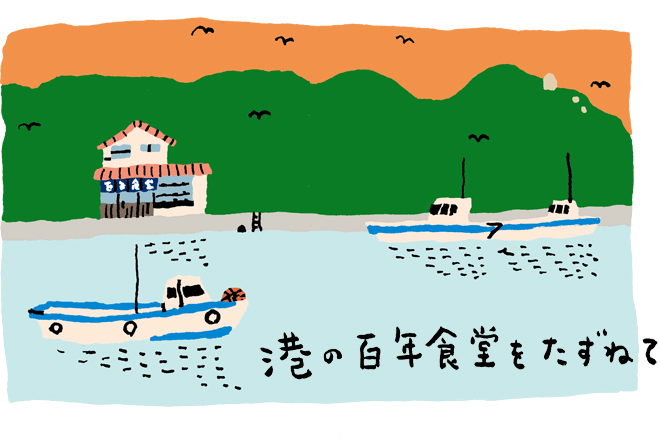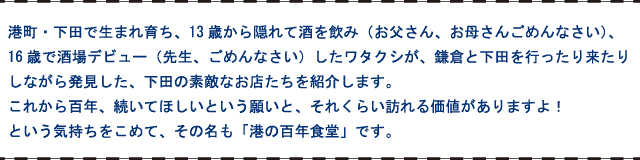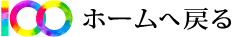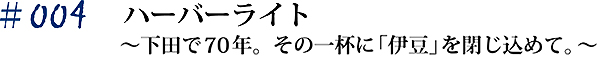
中高生の頃、雑誌『Olive』とマンガ『別冊マーガレット』を愛読していた私。発売日は授業なんかうわの空で、学校が終わると書店まですっ飛んで買い求めていた。そして、そのまま家に帰らず、商店街を直進し港に出ると、船をロープでつなぎとめるための係船柱に腰掛け、ゆっくりページをめくる。家よりも、こうして港風に吹かれ海猫の鳴き声を聴きながらのほうが不思議と落ち着いて読めたのだ。
港に向かう途中、いつも見上げてしまう場所があった。船の舵のモチーフに荒々しい筆致で「ハーバーライト」の手描き文字の看板。石造りの重厚な建物。薬局やおもちゃ屋、雑貨店などが並ぶ、のどかな商店街のなかで、ひときわ異彩を放っていた。スナックなのかキャバレーなのか不明だったが、小娘が近づけない、大人の夜の社交場であることが当時の私にも感じられた。毎年5月に開催される「黒船祭り」には、アメリカからたくさんの水兵さんが下田にやってくるのだが、そのときはこの店の外にまで白いセーラー姿の男性たちであふれていたのを覚えている。
お酒の飲める年頃になっても、あの独特の雰囲気は近寄りがたく、気になりながらも一度も入ったことはなかった。しかし、ここ最近、「あそこの若いバーテンダーがつくるカクテルは本格的なんだ。伊豆で採れるフルーツを使っててさ。つまみも下田らしいものを工夫してて、それが旨いんだよな」
地元に住む何人かの友人にたびたび勧められる。ならばと、下田の新たな扉を開きに、ひとり訪れた。

開店の20時を少し回ったころ。カウンターにはすでに4人のお客さんが陽気な酒を飲んでいた。
生バンドのライブもあると聞いていた店内はかなり広い。スタンディングであれば30〜40名は入れそうだ。テーブル席もあるけれど、バーはやっぱりカウンターがいい。目の前でカクテルをつくってくれるバーテンダーの所作を見たいからだ。
「何にいたしましょう」
先客から離れたカウンターの端に座っていると、バーテンダーで店主の鈴木勝士さんが声をかけてくれた。黒いベストに白いシャツ。彫りが深く、どこかラテンの雰囲気を漂わせている。
「伊豆のフルーツをつかったカクテルがあると聞いたのですが、今日は何がありますか?」
「ちょうど先ほど手に入った稲梓のなごみ果園さんのいちごをつかったダイキリがあります」
なごみ果園の紅ほっぺは食べたことがある。ジューシーで濃厚な、強い味のおいしさだった。ぜひ、それをお願いします。
ホワイトラム(BRUGAL)とストロベリーシロップのボトルを並べ、いちごをすりおろしはじめる。5つのいちごがあっという間にピューレ状になった。たっぷり使われるんですね。そう言うと、「果物が主役のカクテルなので、お酒の量は通常のレシピより少し控えめにしています。そのほうが、いちごの持ち味を楽しんでいただけると思いますよ」と説明してくれる。
シェイカーに氷と材料を入れ、キャップをすると勢いよくシェイク。シャカシャカと氷がぶつかり合う音が響き、そのキレのある所作をもっと見ていたいと思ったがあっという間だった。天使が柄になっているラブリーなグラスに一気に注ぐ。最後の一滴を切ると、その真っ赤なカクテルをスッと差し出してくれた。

とろりとしたいちごの甘み。プチプチした食感を楽しんでいるとほんのり酸味が追いかけ、全体をラムがやわらかく包んでいる。「果物が主役」という理由がよくわかった。いちごのおいしさを引き出すためのお酒なのだ。
「とてもおいしいですね」
素直な感想を伝えると、鈴木さんが白い歯を見せて笑った。
「ハーバーライト」は、いまから70年以上前、オーナー中村彰さんのお父さまが始めた店。最初はダンスホールだった。お酒とダンスが大好きだった初代が「広く踊れる、大人の遊び場を」と、ザ・プラターズの同名曲からその名をつけた。
時は昭和30年代後半。やっと下田-伊東間で伊豆急行の運転が始まったばかりの頃のこと。客の中心は、風街港として下田漁港を利用していた猟師たちと、下田ドックで働く人々だったという。
「ホステスがお客さんをもてなすキャバレーだったときもあるし、ゲイバーだったときもあるよ。いろいろなスタイルを経て自分が店を引き継ぐことになったとき、バーテンダーを7人雇っていた。そのなかに勝士がいたんだ。勝士は群を抜いて腕がよかった。客からもあいつのつくるカクテルはうまいって評判でね。彼にこの店を託そうと思ったんだ」
オーナーの中村彰さんが振り返る。
当時36歳だった鈴木さんは、1年悩んだ。昼間働いていたこともあったが、「ハーバーライト」の名前、歴史があまりにも厚く、重かったことが大きかった。しかし、20歳のころからバーテンダーとしてハーバーライトのカウンターに立ち、沼津の名店といわれるバーでバーテンダーとしての技術を磨いてきた鈴木さん。店の看板を背負う覚悟を決めた。
「カクテルができあがる瞬間がたまらなく好きなんです。だからまたカウンターに立とうと思いました」。
鈴木さんは心底バーテンダーという仕事が好きなのだろう。よりおいしい味を求めて、伊豆のさまざまな果物を取り寄せ、ときに自ら生産者のもとへ足を運び、研究を重ねている。東伊豆の「はるか」、大賀茂の「ライム」、河津の「黄金柑」、松崎の「シークヮーサー」などなど、柑橘天国でもある伊豆の土地柄を存分に活かした魅力的なカクテルは、観光客だけでなく地元の人たちにも評判だ。
研究熱心なのは、酒に合う“バーつまみ”も然り。この日のつきだしは、下田干物の定番、ムロアジを練り込んだチーズだった。生地からつくる自家製ピザにもムロアジをトッピングしたり、須崎産の昆布をつかったペペロンチーノにしたり、金目鯛をエスカベッシュにしたりと地場産品を“バーつまみ”にアレンジしている。
いいバーは、客に愛される。
先客の4人組は、横浜方面からのお客さまだった。ここハーバーライトが好きで、年に何度も訪れるという。鈴木さんとも親しげに話している姿は、まるで地元の常連さんのようだった。あとからやってきたご夫婦は、静岡市のお客さま。わざわざメニューをプリントアウトして持参し、「伊豆の果物のカクテルが飲みたいと思って」と奥さま。「初めてきたけれど、なんだか落ち着くお店だね」とはご主人。そんなふたりの会話に、口を挟むことなく鈴木さんは静かに仕事を続けている。バーテンダーと客の距離感は、それくらいが心地よいと、わたしは思う。
ハーバーライトの詳細情報