第14話作家、下田、そして夜と
作家、下田、そして夜。作家は夜の静寂から夢をつむぎ出す。下田のもうひとつの魅力、それは作家が愛する夜。
「巨漢現る!」
それはある雨の降る日だった。
今日はあの人がやってくる。
外で遊んで帰宅し、家の階段を駆け上ると、二間ある部屋の間仕切りの襖が外され、大きな居間となった畳の上にテーブルが置かれていた。
上座に悠揚として座っているのは、タバコをひと時も離さないようなヘビースモーカーで、カッターシャツ姿の太鼓腹の巨漢を擁し、大きな顔にメガネが乗っている、小松左京さんである。

父と母の結婚披露宴での小松先生
父と酒を酌み交わしながら、小松さんがふと気付かれた。
壁にかけられた黒い塗料で塗られた槍のような棒である。
「なんやあれ」
「あれか・・・」と父は立ち上がり棒を手に持ち、先端のジッパーがついた袋を開ける。
何と中からは出刃包丁が出てきた。
物干し竿のような棒には包丁がついているのである。
父自家製の槍であった。
両手で槍を持った父はそれで宙を突いてみせる。
「なんかあったときのためや」
小松さんはこのときばかりは、太鼓腹を抱えて大笑いされていた。
この頃私はまだ小学校4、5年生で、小松さんの「日本沈没」が話題になった時代のことである。
父と先生との関係は、私がまだ生まれる前、父も母も若く貧しい時代にまで遡る。
どういうきっかけかは知らないが、この時二人は友人を交え京都で会社を作ったそうである。
個性の強い二人は意気投合したようだが、会社は資金難で潰れてしまい、結局その後別々の道を歩むことになる。
多忙を極める小松さんがわざわざ京都の片田舎の拙宅に顔を見せに来られたことで、我が家は驚きと歓喜で大騒動であった。
昔から小松さんのことを、父は「みのる、みのる(本名)」といい、母は「左京さん、左京さん」とよく聞かされていたので、私は小松さんを身近に感じる父の友人として認識していた。
「叶わぬ出会い」
そんな小松さんも、友人の開高健さんが亡くなられ、もう遊び仲間がいない寂しさを抱きながら鬼籍に入られてしまった。
そしてわが父も3年前に逝ってしまった。
あの世で、三人が酒を飲みながら女の話しでもしているのではないだろうか・・・。
小松さんの友人、開高健さんは私が大学生時代にその著作とお人柄をこよなく愛した作家であり、今もって読み続けている作家である。
大学4年生の夏、就職活動で某出版社の入社試験を受けた。
その会社の名物、「三題話」の試験をパスした私は、次の面接でとちってしまった。
「この会社で何をしたいですか?」と聞かれたときに、とっさに考えてもいないことを口走ってしまった。
「文学全集を編集したいです」。
「それなら他の社があるんじゃない」。
もう遅かった。
心の中で準備していた言葉は「開高先生にお会いして、仕事を一緒にしたいです」、であったのに・・・。
悔やまれる・・・。
この言葉を言ったところで受かるとは思っていなかったけれど、どんなに自分で納得できるものであったかは十分理解できていたはずであった。
それにしても、結局、大学卒業後に生前のお二人との対顔は叶わなかった。
これには悔やんでも悔やみきれない思いだ。
卓上ライトに照らされたウィスキーに顔を近づけつつ、叶わぬ邂逅を妄想するのである。
「昔の下田」
小松さんと開高さんという作家の作品に出会ったことは私にとって人生の宝である。
下田に引っ越してきて、どんな作家と新しく巡り会えるかもまた楽しみの一つだし、町がどう変わってゆくかも興味のひくところである。
こちらに来て、先ず印象深かったのは、立原正秋の作品である。
その旅行記「風景と慰藉」の中で、立原は、伊豆、箱根、下田の観光ずれした姿を酷評している。
一例を挙げれば次のようなものがある。
「下田駅前の店で伊勢海老のつくりをたべてみた。桜色の海老の肉はおいしかったが、野菜サラダじゃあるまいし、胡瓜とレタスをつけてマヨネーズをかけてあるのは、どういうことなのか、さっぱりわからなかった。和洋折衷のつもりだったのか。ビールを一本のんで合計二二五十円だった。廉いくいものではない」。
さらにこう断罪している。
「箱根、伊豆は日本の代表的な観光地だが、食べもののまずさはまさに限度にきている、といった感じがする。事実、画一化された食物にうまいものがあろうはずがない」。
この作品が1974年に発表されているので、伊豆急が下田まで開通してから10年以上が経っている頃の話である。
今から40年も前の話だが、何だか耳の痛い話ではないだろうか。
「作家と下田」
立原正秋よりも先に下田に来ていたとはいえ、下田と三島由紀夫のつながりがこれ程までに深いものだとは知らなかった。
横山郁代さんの「三島由紀夫が来た夏」という本の中でそれは明らかにされている。
1960年代から1970年代まで、その最後の日を迎える数年間の夏を、三島は下田で過ごしていた。
彼は夏の1ヶ月を家族とともに東急ホテルに止宿していたのである。
鍋田浜。
パイプが趣味の私は、鍋田浜にある喫茶店「つぼや」さんへタバコを買いに行くのだが、浜辺一帯も彼の出没した場所であったらしい。
自転車をこぎつつ、鍋田の浜に通ずるトンネルを抜けるときに、時々彼の顔が目に浮かぶ。
しかしそれは、昼の顔である。
夜の彼の隠れた顔ではない。
彼は一体何者であったのか?
後半生のその激し過ぎる生き方は何だったのか?
ひょうきんで、人懐っこい三島を発見してその落差を改めて確認したりする。
「夜が下田を作る」
立原も三島も見た下田とは違った下田の姿がある。
夜の9時を過ぎると人通りは少なく、店じまいしている店舗も多い。
彼らが見た観光地下田とは違う姿だ。
闇がむき出しだ。
町が本来持っている昼と夜の顔を下田は取り戻している。
誤解を恐れずいえば、景気が悪いのはよく分かるが、このうら寂しさも町の味である。
不夜城の町だけが町ではない。
この闇夜をどういう風景にしてゆくかは今後の下田のあり方に関わってくるだろう。
何度もいうが、きらびやかさや賑やかさだけが町の持ち味ではないのである。

夜の町の静寂の中で、夢想する。
小松さんの「さよならジュピター」の宇宙船から見た漆黒の宇宙も、開高さんの「輝ける闇」の銃に撃たれた兵士から流れる温かい血が滴り落ちた蒸しかえるベトナムのジャングルも、立原正秋の秋風も、三島が見た下田の太陽も、この静けさの中で立ち現れる。
この暗い夜から下田が生まれ変わってゆくかもしれない。
夢は夜作られる。
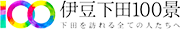

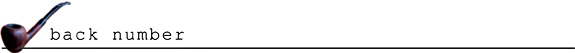


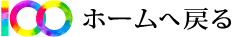
コメントする