第30話「世界のフロンティア 幕末の日本」
世界覇権を狙うイギリス
「神は世界地図が、より多くイギリス領に塗られる事を望んでおられる。できることなら私は、夜空に浮かぶ星さえも併合したい」
この言葉は、イギリスの政治家、セシル・ローズ(1853年―1902年)の言葉であり、その時代のイギリス人の国際情勢への感情の発露である。
19世紀も後半になると、ヨーロッパ列強、特にイギリスの帝国主義の時代となり、蛮行が繰り返される。
その萌芽は、19世紀中葉のクリミア戦争をはじめとする、ヨーロッパ列強の政治的なヘゲモニー(覇権)抗争に端を発する。
当時の国際情勢は、オランダが凋落し、イギリスが国際的な経済活動に邁進し始め、ドイツ、ロシアという列国の海外進出、オスマン・トルコの動揺という問題が明らかになった。
世界の中の日本
アメリカ合衆国を含め、全世界が相互に影響しあう世界になったいたのである。
つまり、アジアの片隅で起きたことも、大国の重大事件となるような、世界的な連動関係があった。
日本も例外ではなかった。
確かに、19世紀中葉に、ゴールドラッシュが起こり、産業革命の先鞭をつけて、太平洋への進出を企てたアメリカ合衆国は、ペリー艦隊を日本へ派遣した。
これは、アメリカの国情だけでの動向ではない。
大きく、世界の情勢とかかわった動きでもあった。
日本は、中国大陸、アジア全体の橋頭保であり、これを抑えることは必須の条件となっていたのである。
西洋の列国が日本でのヘゲモニーを奪取したかったのは、その植民地化でもある。
例えば、日本では、西洋で採掘される比率よりも金の生産が大きいことから、貨幣の交換率で優位に立とうと条約締結が急がれた。
しかし実際は、日本が列国の植民地とはならなかったのである。
誤解を恐れずに言えば、この点が幕末から明治につながりその後の日本の歴史のユニークなところである。
世界の中の下田

船舶の今昔
「それにしてもよ、ありゃー、真黒なクジラずら」
そうやって、下田湾の「黒船」を眺めたものもいたことだろう。
「黒船」。
一隻の大きさの感覚では、下田っ子にわかるたとえで言えば、長さは、漁業市場の端から端まであり、マストの高さは、ベイステージの建物より高く、道路向かいのホテルの頂までに匹敵する。
当時の日本の船舶が今の金目船以下の大きさである、これがどれだけ巨大であったかは想像できよう。
まさにクジラ以上である。
こんなのが、小さな下田湾に幾艘も浮かんでいたのである。
視覚的な衝撃は、世界の大きさだと目には映ったことであろう。
さて、「黒船」がやってきてから、日本は不平等な立場でありつつも、植民地化の流れには巻き込まれず、したたかに生き抜く。
それとともに、非常にたくさんのあちらのものも雪崩れ込んでくる。
日本があの列強の経済市場の一つとなった瞬間であった。
一旗揚げることができた日本
ということは、あちらさんの人の中にも、ここで一旗揚げようと息巻く人がいたとしてもおかしくなかろう。
意識しようとしまいが、日本の中の異国人の心の中にはそんな野心があったのではなかろうかと思うのである。
なにも悪人、善人を拾い上げて揶揄するつもりはない。
ただ、当時の日本は、そういうひとからしてみればフロンティアであったことは確かである。
下田の玉泉寺のアメリカ合衆国領事館で働く、ヒュースケンはどうだろうか?
領事ハリスの片腕として、通訳をしながら交渉に助言する、今でいう外交官のようなこともやっていたわけだが、下田に来た時には24歳、血気盛んな青年であったようである。
「(馬一頭手に入れて)サラブレッド1頭にしては何という大金!このぶんならどうやらやってゆけそうだ。
日本にきて、まず下男を雇った。
こんどは馬持ちだ。
この調子だと、自分の馬車を持って皇帝の一人娘に結婚を申し込むことにもなりかねない。
そうなると俺は植民地総督だ・・・」。(青木枝朗訳「ヒュースケン日本日記」より)
横濱の居留地で写真スタジオを開いた、イギリス人、フェリーチェ・ベアトはどうか?
来日した当時はまさに横濱が誕生するときであり、その地で彼は実際に実業家として名をはせていた。
お吉はどうだ?
下田を後にして、新天地、横濱で暮らしていたではないか。
しかも、横濱には多くの下田の人が住み、この地の開港に尽力していた。
日本人にとって、また異国人にとって、横濱がフロンティアであったのである。
* 最後に、私はここで一言いいたかったことがある。
列国の埃渦巻く進軍に次ぐ進軍のなかで、零れ落ちたもの、失ったもの、切ないもの、小さなもののことである。
そうした虐げられたものたちも声を上げる。
大げさなようであるけれども、そして一方的に支持するわけでは決してないけれども、列国で起こった不平等・不自由・権利の消失などに対抗して、新しい価値観が誕生した。
そう、社会主義、共産主義という今では左翼と名の付くものが、被抑圧者を代弁するようになる。
破壊される遺跡、奪い取られた宝玉と人の命。
与えられたアヘン。
持ち込まれた病気。
などなど。
弊害が弊害を積み重ねていった。
私が気がかりなのは、その当時の人が忘れそうになる「心」。
目新しいものばかりに追われ、喰うのもままならずただひたすら働き、失うもの。
何か、時代は違うけれども、スマホに熱中する、電車の乗客を見て、当時の熱狂した日本人の姿も重なり合うように見えるのである。
辺境の地を開拓するのでも、心の余地・僻地(the back country)を失いたくないものである。
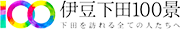

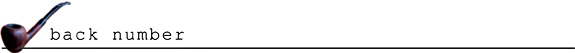


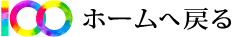
コメントする